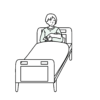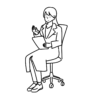1.無痛分娩とは
麻酔薬を用いてお産(分娩)時の痛みを軽減する方法を「無痛分娩」といいます。
お産に対する不安・心配をやわらげて産後の体調回復も早く育児へスムーズに移行しやすくなる効果が期待できます。
麻酔量を調整し痛みを和らげながらも最低限の感覚は残す場合があります。痛覚を全て遮断してしまうと、分娩の進行を妨げる恐れがあるためです。
最低限の感覚を残すことで、本来の陣痛の痛みを和らげつつ安全に分娩を進めることができます。麻酔薬は背骨のあいだに細いチューブを挿入し投与します(硬膜外麻酔法)
無痛分娩のメリット
- 分娩時の痛みが和らぐ
- 出産に対する恐怖心が和らぐ
- 緊張や不安から起こる体力消耗が抑えられる
- 体力消耗が抑えられることで産後の回復が早くなる
無痛分娩のデメリット
- 麻酔処置をしても痛みを感じることがある
- 分娩が長引いてしまうことがある
- 発熱、頭痛、痒みなどが起こることがある
- 稀な合併症を引き起こすことがある
(詳細はお渡しする説明文に記載しております)
麻酔の効き方や痛みの感じ方は個人差があるため、麻酔処置をしても痛みを感じることがあります。
また、麻酔が効き始めるまでは痛みを感じてしまうなど、分娩における痛みを全て無痛にできる訳ではないことをご理解ください。
麻酔処置をしても痛みを感じる場合、麻酔の追加や管の入れ直しなどの処置を行うことがあります。
また、麻酔処置をして痛みを和らげることで陣痛が遠のき、分娩時間が長くなったり、麻酔後に発熱したりするケースもあります。
適時、医療の介入によって安心、安全にお産を勧められるよう処置いたしますのでご安心ください。
2.対象となる妊婦さん
当面の間は、
- 「経産婦さんのみ」を対象とさせていただいております。
- 「計画分娩」で実施いたします。
計画無痛分娩は、十分な分娩監視が必要なため(平日指定日の日中のみ、休日・夜間での対応はしておりません)、前日入院となります。前日の入院管理を含み、通常の分娩費用に12万円が加算されます。
なお、当院では安全な計画無痛分娩を行うために施行条件がございます。また条件の適応があっても、必ずしも計画実施通りにはいかないことがあることをご本人とご家族様にご承知をいただき、文書によるご同意をいただいております。
【施行条件】以下の条件と母体の状態をみて医師が総合的に判断します。
- 妊娠37週以降
- 頭位(逆子は適応できません)
- 既往子宮手術歴(帝王切開や子宮筋腫手術など)がない
- 分娩時母体BMI:28未満【BMI:Body mass index = 体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)】
例えば)身長155㎝の方でBMI<28という条件は、
→BMI 28×1.55×1.55=67.27となり 体重が67.27㎏未満となります。
- 血液凝固異常(妊娠後期の採血で血小板数などが少ない場合)がない
- 腰・背骨の手術歴(腰椎ヘルニアなど)がない
- 子宮頸管の熟化・児頭下降が十分と医師が判断した場合
- 「選択的計画無痛分娩(無痛分娩)説明会」の動画視聴と承諾
- なお安全管理上、月間の分娩数に制限があり規定数に達した時点で、予約を締め切らせていただきますことをご了承ください。当院の選択的無痛分娩(無痛分娩)の説明会をご受講の上、スタッフにまずお申し出ください。
3.安全な無痛分娩に向けた取り組みについて
当クリニックでは、無痛分娩を安全に実施するために下記管理を実施しております。
①麻酔薬の安全管理について
- 硬膜外カテーテル(麻酔薬を持続的に投与するチューブ)が正しい位置に固定されているかを確認します。正しく確認されない場合は、入れ直すこともあります。
- 本番で使用する薬品より濃度が薄く少ない量で体調の異常が出現しないかチェックします。安全が確認できない場合は、次の段階へ進みません。
- まずは少量投与で異常がないことを再確認の上で必要量を投与します。
- 頻回に麻酔効果を確認し、異常の早期発見に備えます。
②子宮収縮薬(いわゆる陣痛促進剤)の安全管理について
- 麻酔薬の使用は鎮痛効果が発揮される一方で、多くの場合陣痛も弱くなるため、自然の陣痛を補強する目的で子宮収縮薬を使用します。
- 子宮収縮薬は点滴で使用します。少ない量から開始して母体と胎児の異常が認められないことを確認しながら階段的にゆっくり増量します。
- 有効な陣痛が得られたと判断したら、その量を維持しむやみに増量を続けません。
- 頻回に子宮収縮薬の使用による効果を確認し、異常の早期発見に備えます。
- 経過中胎児心拍を連続でモニタリングし、異常の有無を管理します。
③不測の事態が発生した時の対応
- 母体および胎児の状態に危険がおよぶ恐れが発現した時点で薬剤の使用は中止し、母体・胎児の安全管理を優先します。
- 川口市立医療センターに連絡し、転院または緊急手術を行うか協議します。
- 緊急搬送の方針となった場合は、スタッフが同乗し救急車で移動します。
- 緊急度が低くても麻酔による影響が蔓延する場合は川口市立医療センターまたは関連診療科へ連絡し、転医受診となる場合があります。
当院の無痛(硬膜外麻酔)分娩は、北里大学病院産科麻酔に準じて取り行っています。
当院の無痛分娩に関する情報公開はこちら
4.監修医師のご紹介
- 麻酔科 三島仁(みしまひとし) 慈恵会医科大学麻酔科 高山整形外科 所属
【所属学会】日本麻酔科学会、麻酔科指導医 専門医(23-02033)
-
産科麻酔 天野完(あまの かん)
主な所属学会
日本産科婦人科学会功労会員、日本新生児・周産期医学会功労会員、
日本産科麻酔学会名誉会員 (会長:2003~2014年、監事:2014~2023年)
神奈川県産科婦人科医会名誉会員、日本妊娠高血圧学会功労会員
略歴
| 1974年3月 | 名古屋市立大学医学部卒業 |
| 1974年4月 | 北里大学病院産婦人科レジデント |
| 1981年4月 | 北里大学医学部産婦人科講師 |
| 1983年10月 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 産婦人科部長 |
| 1991年4月 | 北里大学医学部(産婦人科講師)に復職 |
| 1999年4月 | 北里大学病院産科病棟主任、周産母子センター主任 |
| 1999年5月 | 北里大学医学部産婦人科助教授 |
| 2009年4月 | 北里大学医学部産婦人科診療教授 |
| 2013年4月 | 北里大学病院産科科長、周産母子成育医療センター長 |
| 2014年4月 | 北里大学医学部客員教授(~2023年) 医療法人社団湘洋会 産婦人科吉田クリニック理事、副院長 |
| 2024年4月 | てるて産科クリニック |
| 2014年 | 平成26年度産科医療功労者厚生労働大臣表彰受賞 |
ご挨拶
周産母子センターで周産期医療、無痛分娩による分娩管理に携わり、一次施設で1,000例以上の無痛分娩管理を行ってきた経験を基に、硬膜外鎮痛法による無痛分娩で痛みから解放され安全で快適な分娩体験が得られるようサポートいたします。
★金井雄二(かない ゆうじ) 堀病院(横浜市瀬谷区) 院長
前 北里大学医学部産婦人科 産科講師
協力医師のご紹介
黒須不二男(くろす ふじお) ナラヤマレディースクリニック(上尾市)院長
佐藤聡二郎(さとう そうじろう) セイントマザークリニック(仙台市)院長
檜垣博(ひがき ひろし) かわぐちレディースクリニック(川口市)院長
当クリニックの無痛分娩では、実施中の患者さまに専属のスタッフが担当します。
なじみの顔のスタッフに、麻酔薬の効き具合や分娩進行の程度をじっくり確認しながら相談することで、ご安心とご満足いただけるよう心がけています。
お陰様をもちまして開院以来、一度も事故は発生しておりませんが、気を緩めることなく随時研鑽を積み重ねながら磨きをかけて、
安全と信頼の実績を積み重ねてゆきたいと存じます。
さとうレディースクリニック
麻酔分娩麻酔管理者 佐藤 倫也